モンゴルでの肝炎対策再開 「佐賀方式」普及へ本腰 佐賀大肝疾患センター
- mongoliawalker
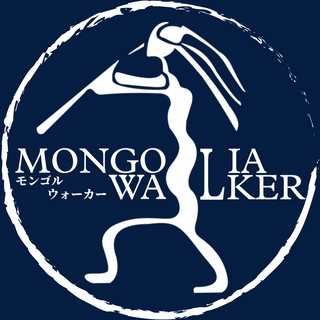
- 2022年5月17日
- 読了時間: 2分
更新日:11月23日

佐賀大医学部附属病院肝疾患センターは5月から、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2019年から中断していたモンゴルでの肝炎対策事業を再開する。17年から始めた事業の成果を踏まえ、今回は首都ウランバートルから離れた地方で肝炎の実態を調べる。モンゴルはウイルス性肝炎の感染率が世界的に高く、早期発見から治療につなげる「佐賀方式」の普及を本格化させる。
外務省が4月、モンゴルの感染症危険情報を「渡航中止勧告」のレベル3から、不要不急の渡航の自粛を求めるレベル2に引き下げたことを受けて現地事業を再開することにした。5月中旬から約2週間、モンゴル東部のスフバートル県に看護師を派遣。肝炎ウイルス陽性者に対してエコー検査や肝臓の硬さを計測するフィブロスキャンなどを行い、実態調査を進める。
アジアなどで医療ボランティアを続けてきた旧佐賀医科大の香月武名誉教授がモンゴルのロータリークラブから肝疾患対策に関する相談を受け、クラブの活動の一環として17年に現地を調査したのがきっかけ。翌年にはモンゴルの医師が佐賀県を視察するなど活動が広がった。治療薬の普及などモンゴル政府の取り組みもあり、肝炎の治療が進んでいるという。
ただ、モンゴルの人口の4割以上が暮らす首都ウランバートルと地方との格差は大きい。国土の広さや検査機器不足もあり、地方在住者や遊牧民らへのアプローチは進んでいない。今回訪問するスフバートル県も、ウイルス性肝炎の感染率が高いという。
佐賀県は人口10万人当たりの肝がん死亡率で全国ワーストが続いていたが、18年にワーストから脱した。背景に、関係機関が連携して検査と受診、治療のサイクルを回す佐賀方式がある。患者のサポート役を担う「肝炎医療コーディネーター」の役割も大きく、モンゴルでも19年までの2年間に168人を養成した。
同センターの高橋宏和センター長(45)は「肝炎対策で重要な早期発見のスキームづくりのため、佐賀の経験を役立てたい」と話す。(江島貴之)
佐賀新聞



















































コメント